*イベントレポート前半はこちら。
*Click here to view the English page.
パネルディスカッション 「AI前提の健康・医療」
モデレーター:
- 村井純, 慶應義塾大学KGRI サイバー文明研究センター共同センター長
登壇者:
- 尾身茂, 公益財団法人結核予防会理事長
- 湯澤由紀夫, 藤田医科大学学長
- 鈴木蘭美, ARC Therapies株式会社社長CEO
- 浅井大史, 株式会社Preferred Networksシニアリサーチャー・インフラ戦略担当VP(オンライン)
- 山本龍彦, 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
- 橋本正弘, 慶應義塾大学医学部専任講師
- 橋田浩一, 理化学研究所 革新知能統合研究センター グループディレクター
- 鈴木晋, 株式会社Cure App開発統括取締役/医師
- 福西宗憲, アナウト株式会社 グローバルプログラム ディレクター
 ◯村井 本日のテーマは「AIを前提とした健康・医療」についてですが、私が一番強く持っている問題意識は、こうした技術を私たちが長年かけて作ってきたということです。また、パンデミックの経験もあり、人々の理解も広がって、技術自体もどんどん進化しています。私たちが思い描いていた理想に近いものを現実として社会で共有できるようになってきたと感じています。そして、健康や医療というとても大事な領域でこうした技術が活用できないのであれば、開発に携わってきた私たちとしては「何のためにこれまでやってきたのか」という思いもあります。
◯村井 本日のテーマは「AIを前提とした健康・医療」についてですが、私が一番強く持っている問題意識は、こうした技術を私たちが長年かけて作ってきたということです。また、パンデミックの経験もあり、人々の理解も広がって、技術自体もどんどん進化しています。私たちが思い描いていた理想に近いものを現実として社会で共有できるようになってきたと感じています。そして、健康や医療というとても大事な領域でこうした技術が活用できないのであれば、開発に携わってきた私たちとしては「何のためにこれまでやってきたのか」という思いもあります。
一方で、医療に関わる方々の視点から見れば、いよいよ夢を実現するような環境が整ってきたのではないでしょうか。技術を作ってきた側から見ても、医療現場から見ても、今は言い訳できない段階にきています。
まず、AIの「現在地」について、橋田さんにお伺いします。橋田さんはこの分野の研究者として長年取り組んでこられており、日本におけるAI研究の初期から中心的な役割を担ってこられました。2025年現在の状況をどのようにお考えでしょうか?
◯橋田 ChatGPTが登場してからもう3年ほど経知ますが、そこからの流れを見ていると、思っていたよりも研究は進んだ印象を持っています。ただ、いわゆる「汎用人工知能(AGI)」について、現在のテクノロジーをそのまま発展させていった先には到達できないと考えています。今のディープニューラルネットワークを拡張したとしても、人間の知能を超えるような存在を生み出すことはできないと思います。現在のAIは要約や翻訳など、表層的な情報処理においては大きな力を発揮していますが、いわゆる人間の批判的思考力に相当するような能力は持っていませんし、それを実現できるような技術的見通しも、現時点では存在しないと考えています。
◯浅井(オンライン) 確かに、AGIに到達するにはまだ多くのステップが必要だと思います。一方で、トランスフォーマーの登場によって、コンピュータ資源をより効率的に活用できるようになりましたし、AIの性能は着実に向上していると認識しています。特に、ChatGPTのようなツールが、誰でも自然なインターフェースとして使えるようになったという点は、非常に大きなブレークスルーだと感じています。今では自然言語や音声でAIとインタラクティブなやり取りできるようになっています。こういったインタラクションの変化は、AIが我々の生活や仕事の基盤になり得る段階まで来ていることを示していると思います。

◯村井 ありがとうございます。ここまでは技術面から見たAIの現在地について伺いましたが、医療現場では実際にこの技術を活用していく中で、さまざまな課題に直面しています。藤田医科大学はAIなどの最新のテクノロジーを取り入れるチャレンジをされてきましたが、湯澤さん、病院という現場でこのような技術を取り入れる観点から、AIの現在地について、どのようにお考えですか?
◯湯澤 私としては、しばらくは医療や研究の支援を目的に、しっかりAIを社会実装していく段階だと感じます。そして、業務としてAIを活用するためには、やはり医療データが二次利用されるという前提が必要です。私たちの病院では、病院長が「何のためにAIや医療DXを進めるのか」という目的を、すべての教授に丁寧に説明し、各診療科が一体となって取り組む体制を築いています。これがなければ、大学や病院の中でAIを活用する土台は整いません。その点については病院長をトップとして組織的なガバナンスが効いていると感じています。
また、臨床試験についても、合成データを活用することで、これまでリアルワールドデータが得にくかった希少疾患の研究にも新しい道が開けると期待しています。臨床研究、教育、研究支援の分野で、私たち大学・病院としてAIをしっかりと使いこなし、社会に実装していく必要があると考えています。
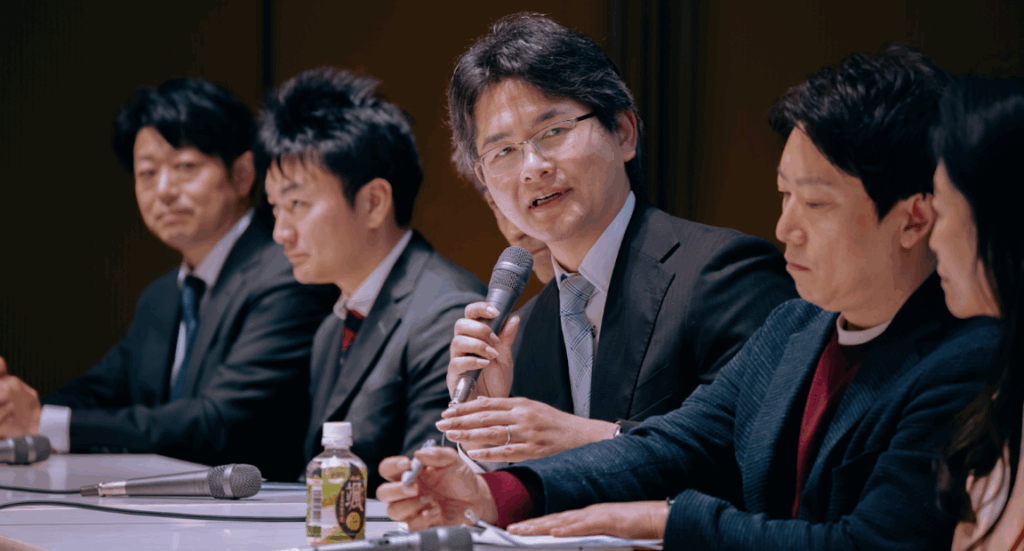
◯橋本 藤田医科大学のように、退院サマリーを作ることについても、全診療科を巻き込んだ取り組みは、慶應ではまだ実現できていません。プロンプトを自分で工夫して、ある程度自発的に広げていこうとする人たちが先行して進めているという段階です。全員が同じ方向を向いて進んでいくのは、やはり難しい面があります。ただ、軸足として感じているのは、それは「医療従事者の負担を軽減しよう」という視点と、さらに「患者さんのためになることを実現しよう」という方針のもとで、AIの導入が進められています。
◯村井 先ほど山本先生がおっしゃっていた「個人界」と「集合界」という考え方は、個人情報をどう捉えるかという上で非常に重要な視点だと感じました。個人情報保護法についても個人界の考え方だけで縛られてしまっていたことで、例えば医療情報の将来的な活用の可能性を閉ざしていたのではないかという感覚が、直感的にあります。この「個人界」と「集合界」という考え方は、国際的なスタンダードとして受け入れられてきているものなのでしょうか?
 ◯山本 EUの考え方についてですが、基本的には「個人に直接関係する情報」は、個人がコントロールできるようにしようという考え方があると思います。これは、データポータビリティ権などの発想ともつながっています。一方で、個人に直接返ってこないような、すぐには個人に影響を及ぼさない情報については「集合界」のデータとして扱い、産業データも含めて公的な資源として積極的に活用していこうという考え方もEUにはあります。そうしたメリハリ、使い分けは、EUではある程度整理されてきているように思います。
◯山本 EUの考え方についてですが、基本的には「個人に直接関係する情報」は、個人がコントロールできるようにしようという考え方があると思います。これは、データポータビリティ権などの発想ともつながっています。一方で、個人に直接返ってこないような、すぐには個人に影響を及ぼさない情報については「集合界」のデータとして扱い、産業データも含めて公的な資源として積極的に活用していこうという考え方もEUにはあります。そうしたメリハリ、使い分けは、EUではある程度整理されてきているように思います。
ところが日本では、このような違いを十分に意識せずに議論が進んでしまっていたため、さまざまな誤解が生まれているのではないかと感じています。たとえば「集合界」のデータも「個人界」のものとして捉えて、すべてに個人の同意が必要だと考えるような方々もいます。一方で、医療関係者はなるべくリアルなデータとして個人情報を活用したいので「個人界」の情報もパブリックな資源として扱おうとする傾向が見られます。どちらの側も明確な区別がないまま議論してきたことで、結果として「トラスト(信頼)」が十分に築かれなかったのではないかと感じます。
◯村井 2016年には「官民データ活用推進基本法」という法律が作られました。この法律の目的は、まさに集合的なデータの利活用を促進することだったのですが、うまく機能しなかったというのが実情です。これはなぜ機能しなかったのだと思われますか?
◯山本 なぜ機能しなかったのか、これはあくまで私見ですが、日本の個人情報保護法は「過剰かつ過少」と言われています。つまり、本当に守るべきものは守れていないのに、逆にあまり重要でないものについては過剰に保護されていて、結果としてグロテスクな形で成長してしまったという指摘もあります。
◯村井 「官民データ活用推進基本法」は、どの省庁もガバナンスが効かなかったのか、結局は議員立法という形になりました。これは、さきほどの「ガバナンスの欠如」とも関係してくるかもしれません。
デバイスの発展によって、AIの活用においても個人側のデバイスでの処理も可能になってきています。このような発展の中で、個人データ「個人界」と社会データ「集合界」の関係性について、鈴木晋さんはどのようにお考えですか?
◯鈴木晋 私は「医療情報」と「生活情報」は少し分けて考えるべきだと考えています。たとえば、治療用アプリが扱っている情報は「バイオ・サイコ・ソーシャル」な情報であり、その人が朝働いているのか、普段から歩く習慣があるのか、といった生活の様子が治療の中で重要になります。そういった情報はエッジデバイスに保持して、アドバイスの参考に使い、メディカル・バイオロジカルなデータに関しては、しっかりフィードバックして、医療の発展のために活用してもらうべきだと考えています。
◯村井 少し話は変わりますが、ロボットによる手術支援の画像判断を行うAIの技術を開発されているのが、福西さんです。自己紹介も兼ねて、その技術の進化がどのあたりまで来ているのか、お話しいただけますか。
◯福西 私たちは手術支援向けのAIの開発を行っています。現在、手術ではロボットや腹腔鏡といった低侵襲な治療方法が広がっており、日本の先生方の技術も非常に高く、高品質な治療が提供されています。それでもやはり合併症などのリスクはゼロではなく、そうしたリスクを可能な限り抑制し、安全な治療を実現したいという思いがあり技術開発を行っています。
村井先生から「AIの現在地はどのあたりか?」という質問がありましたが、医療向けAIの開発はまだ黎明期にあると考えています。たとえば、SaMD(Software as a Medical Device)の制度面や、個人情報の取り扱いといった法制度も、ようやく整備が進み始めたところです。
◯村井 ロボット手術では、操作データを蓄積・学習すれば、将来は熟練医の技術を再現可能になります。藤田医科大の宇山 一朗先生や須田 康一先生方からうかがった「サージカル・インテリジェンス」および、ダヴィンチの手術データは誰のものかという議論が以前のセミナーでありましたが、開発元のIntuitive Surgical社が大量のデータを保持していると思われます。松本先生、ご見解をいただけますか?

◯松本 はい。ダヴィンチの関節の動きなどのデータは、米国本社に送られて解析されています。藤田医科大の宇山先生の手術と他医師の比較も可能で、実際に行われているようです。ただ、その結果の具体的な活用法は私には分かりません。
◯村井 AI開発では、どこにデータがあるかが非常に重要です。日本でロボットが開発されれば、大きな意義があります。田中さんのお話にもあったように、国産技術の価値を高めていきたいと考えています。
◯湯澤 私たちも同様の議論をしています。熟練医の手術ログをAIが学べば、他の外科医も高い技術を再現可能になるかもしれません。その技術の権利は誰に属するのか? 現在は企業に帰属していますが、それで良いのか疑問です。大学や医師の権利を守り、開発に活かす必要があります。アカデミアとしても発信が重要です。
◯山本 医療現場にも「責任スポンジ」の問題があります。事故が起きたとき、企業は責任を回避したくなるため、形式的に医師を配置したがる。しかし、医師がすぐに介入できない場面もあり、その存在が責任吸収のためだけになる恐れもあります。これは医師の尊厳にも関わる問題で、リスクの分担や責任の枠組みの再設計が必要です。
◯村井 責任の所在は難題です。特にインターネット接続後はPL法ではカバーしきれません。これは知的財産(IP)とも密接に関わり、誰が責任(PL)を負うかも重要です。責任の“スポンジ”役が保険か他の仕組みか、今後の課題です。
◯尾身 先ほどのプレゼンでもありましたが、AIが登場したことで、人間がバッファー(緩衝材)として立ちふさがらなければならないという構造が生まれてきています。本来、人間のためにあるはずのAIによって、逆に人間が負担や責任を背負わされるようになってしまう。これは法的な問題であると同時に、人々の価値観の問題でもあり、極めて難しい課題です。
◯村井 社会の中でAIをどう使っていくか、その最もクリティカルな領域の一つが医療であり、ここで解決された課題は他の領域への社会的な応用可能性も高く重要です。このように前へ進むためには、医療産業、大学、研究機関、政府など、さまざまなプレイヤーが連携して取り組んでいく必要があります。デジタル政策の文脈は常に、サイロ化した社会の中で、異なるセクター同士を横につなぐ仕組み、すなわち新しいガバナンスの構築が求められています。AIと医療を取り巻くマルチステークホルダーのそれぞれの役割や責任についてどなたかご感想はありますか。
◯橋田 これからはAIとの対話がユーザーインターフェースの中心的な存在になります。AIが私たちの間に入りサービスを繋いでくれる。その結果、従来のアプリやウェブサイトは徐々に姿を消し、あらゆる産業において顧客との接点がAIに置き換わっていく。特に中小規模の事業者から、そうした変化が先に起こっていくのではないかと思います。そのような状況において、規制が本格的に議論されるのは、おそらく10年後くらいからではないでしょうか。しかし、教育や医療といった分野はそう簡単には動きません。医療や教育を、こうしたパーソナルAIとどうつなげていくかが、今後大きな課題として浮かび上がってくるのではないかと考えます。
◯村井 尾身先生、黒川先生は、まさに政府の中で重要な仕事を担ってこられた方々ですので、そのご経験をふまえて、今後どのように取り組んでいくべきかをぜひ伺いたいと思っています。

◯尾身 私の提案としては広くステークホルダーを巻き込んだ、じっくりとしたオープンフォーラムのような場を設けることです。この場にいる先生方のような方々が中心となり、その場を牽引していただければと思っています。
私がWHOでの経験から日本が絶対に学ぶべきだと思ったことは、複雑ですぐに解決できない問題に対して「合意できたこと」「まだ合意できていないこと」を一つ一つ明確に整理し、紙にして共有するというプロセスです。その際には、専門用語を分かりやすく伝える「翻訳者」の役割も必要です。また、そこには「人々がどう感じているのか」という感情の部分もきちんと考慮する必要があります。
日本社会はどうしても、短期的な動きになりがちです。1回議論して終わり、熱くなってもすぐ冷めてしまう。しかし、5年、10年というスパンでじっくりと向き合う必要があるでしょう。そして、翻訳者、ファシリテーターのような役割を果たす人が必要です。丁寧な対話のプロセスこそが、これからのAIの社会に必要だと考えています。
 ◯黒川 医師は必要不可欠な存在で、国によって医療制度の成り立ちは異なります。日本は自由に病院を選べる特殊な制度を持ち、その多くが公的資金で支えられています。しかし、高齢化と少子化が進む中で、この仕組みが持続可能か再考すべき時期に来ています。
◯黒川 医師は必要不可欠な存在で、国によって医療制度の成り立ちは異なります。日本は自由に病院を選べる特殊な制度を持ち、その多くが公的資金で支えられています。しかし、高齢化と少子化が進む中で、この仕組みが持続可能か再考すべき時期に来ています。
◯村井 これまでの医療のやり方を続けるのは限界があります。制度改革には既得権の問題もありますが、インターネットの普及のように、多くの人に支持される技術は制度に先行して広まることもあるでしょう。大切なのは、丁寧にコンセンサスを築くことです。
◯山本 信頼の構築には、法整備よりもまず社会的なムードが重要です。AIは定量的な処理が得意でも、感情や価値観といった定性的な対応は難しく、リスクも伴います。だからこそ、医療・法・哲学の領域を越えた対話を通じて、信頼を育てていくことが大切です。AIの導入にはボトムアップの社会的合意が不可欠です。尾身先生がおっしゃっていたような「対話」の重要性は非常に高いと感じています。
◯村井 「透明性」は「対話」と並んで重要です。どんな技術が使われ、誰にどう影響するかを明確にすべきですが、ここで鍵になるのが「標準化」です。同じ技術を多くの人が使えばコストが下がり、恩恵が広がりますが、特許による囲い込みは価格高騰のリスクにもつながります。インターネットは標準化により低コストな参入環境を実現しました。医療技術も同様に、対話と透明性が「安心」と「信頼」を生み、それが普及に繋がると考えます。
またルール形成の観点からは、医療では国境がルール形成に影響する一方、インターネットは国境を越えて発展してきました。結果として、医療のようなナショナルな空間と、ネットのグローバル空間が共存しています。そうした中で、日本でのAI活用が世界にどう貢献できるか、また海外のAIが日本に本当に合っているのかといった視点が重要になります。
このように、私は日本国内のドメスティックな空間と、グローバルあるいはインターナショナルな空間との関係を、どう整理しながら考えていけばよいのか、という点に関心があります。
しかしまずは、健康分野と医療分野の両分野のつながりについて、どう考えていけばよいのでしょうか。

◯鈴木晋 健康分野と医療分野のつながりは、とても興味深いテーマだと考えています。
私たちのプロダクトの中でも、禁煙や高血圧といった領域は「予防」が可能であり、私たちはより広く「健康」という概念の中でのアプローチを目指しています。そのため、医療機器として提供している製品がある一方で、同じアプローチを用いた「予防」目的の非医療機器の製品も展開しています。社会的には医療と健康の間に明確な線引きがありますが、私たちはその間にある“グラデーション”に注目しています。
現実的な面として、医療は全国に医療機関が存在しているため、ビジネスとして展開しやすい側面があります。保険診療の枠組みに乗ることで、1度承認されれば全国展開も可能になります。その意味で、医療機器としてのビジネスには大きな価値があると考えています。 一方で、本日DeNAさんが紹介されたような健康関連のサービスも、また異なる形で同様に大きな価値を持っていると思います。
◯村井 医療という分野は、日本が誇れるものであると皆さんおっしゃっていますが、一方で、これは高度な国費投入、たとえば皆保険制度によって成立しているバランスでもあります。これは先ほどの黒川先生のお話からも明らかでした。
その上で、私たちは、やはりこのAIによって変わりゆく健康と医療の世界において、日本だからこそできる良いものがあると信じたいというエモーショナルな思いが私にはあります。もしそれが実現できるのならば、それを国際的に展開し、世界に貢献していくという道も考えられるはずです。そうした動きをどう育てていけばよいか、皆さんにぜひ議論していただければと思います。
◯福西 外科領域におけるAIの視点から見てお話しさせていただきますと、日本には非常に大きな強みがあると考えています。なぜならば、日本の手術は非常に丁寧であることは間違いありません。医療現場から得られるデータの質は非常に高く、AIを活用する上でのアドバンテージになると考えています。
一方で、それを世界に展開していくにあたっては、特に「健康」に関する分野は文化の影響が大きく、難しさもあるのではないかと感じています。ただし「医療機器」などのより臨床的で客観性のある領域については、身体構造は世界共通ですし、世界の医療機器メーカーは基本的にグローバル企業がほとんどのシェアを占めていますから、我々はそこに挑んでいかなければならないと思っています。世界に挑戦したいという思いは強く、立ち止まってはいられないと考えています。
◯鈴木晋 それとは対照的な意見も、私たちの社内ではよく議論されています。私たちが手がけている「治療アプリ」という領域は、特にサイコロジカルやソーシャルな側面に大きく影響を受ける分野です。実は私たちもアメリカ展開を目指していたのですが、実際にはなかなかうまくいきませんでした。
たとえば、日本は非常にハイコンテクストな文化で、言語と文化が密接に結びついており共通理解のもとで治療を設計できます。でも、アメリカは人種的にも文化的にも多様性が高く、アメリカ人として共通する文化がそもそも存在しないという難しさがありました。このように、治療アプリのように心理的・社会的要因が大きく影響する分野においては、ローカルに根付く部分があり、グローバル展開の困難さを強く感じています。
◯鈴木蘭美 私たちの治験は日本からスタートしていますので、取り組みの起点は確かに日本になると思います。遠方から東京の病院に来てくださる方もおられますが、長旅の後に強い治療を受けると、どうしても治療効果が下がってしまうのではないかという懸念があります。「健康」と「病気」をきっちり白黒で分ける必要はなく、むしろ、メンタルヘルスや食事、睡眠といった日々の生活要因すべてが、患者さんのウェルビーイングや治療効果に関わっているのではないか、と強く感じています。
◯浅井(オンライン) 弊社が開発しているLLM(大規模言語モデル)は、日本語での性能向上を主眼においており、日本語のデータを非常に多く使っています。世界的に見ると、LLMの主な開発拠点はアメリカや中国などですが、そういったグローバルモデルは、文化的な背景が必ずしも反映されていないことが多いと感じます。インターフェイスは世界共通に揃えられたとしても、モデルの中身、つまりどのようなデータでどのような応答が形成されているかという点では、英語圏や中国語圏を中心とした思考に引っ張られているような印象を受けます。特に医療データに関しては、その国や地域の文化に即したモデルを作っていく必要性を感じています。
また、国によってAI学習に対する考え方や規制も異なります。こうした違いを踏まえつつ、人々がこの基盤モデルになら貢献しても良いと思えるような、透明性(トランスピアレンシィ)や説明責任(アカウンタビリティ)をどう確保するかが重要であり、仕組みを整えていく必要があると考えています。
◯村井 ここを出発点として「ご自身は何をしていこうと思いますか」ということを一言ずつお聞きできればと思います。
◯福西 なかなか難しいところではあるのですが、私たちはまだまだ発展途上の領域ですが、本気で世界に向けて挑戦していきたいという思いで、今取り組んでいます。ぜひ、皆さまからご指導いただければ幸いです。
◯鈴木晋 やはり生成AIネイティブなアプリを作っていきたいという思いがあります。橋田さんがおっしゃっていたように、将来的にはインターフェースは共通化されていくと治療アプリも、承認が必要な部分はモジュール化されて、アルゴリズムの部分だけを認可して、インターフェース自体は自由にデザインしてよいという時代が来ると思います。そうした未来を見据えて、対話型の新しい治療アプリの開発に取り組んでいきたいと考えています。
 ◯橋田 先ほどもお話しした通り、現在は自治体との連携を起点に進めています。これは、自治体が住民のデータを囲い込まず、分散型のサービスが展開しやすいこと、また地域の中小企業とも連携しやすいという背景があります。一方で、村井先生もおっしゃったように、医療制度は国ごとに異なる一方で、インターネットやデータ、アルゴリズムはグローバルな存在です。一部の国では医療データの越境移転を制限する法律もありますが、それは事業者に対する規制であって、個人が自分のデータをどう扱うかまでは制限していません。つまり、個人が自分のデータを保持していれば、それを他国に持ち込んで治療を受けるといったことも可能なのです。インターネットの力を活用すれば、国境を超えた医療サービスの提供が現実のものになるのではないかと期待しています。
◯橋田 先ほどもお話しした通り、現在は自治体との連携を起点に進めています。これは、自治体が住民のデータを囲い込まず、分散型のサービスが展開しやすいこと、また地域の中小企業とも連携しやすいという背景があります。一方で、村井先生もおっしゃったように、医療制度は国ごとに異なる一方で、インターネットやデータ、アルゴリズムはグローバルな存在です。一部の国では医療データの越境移転を制限する法律もありますが、それは事業者に対する規制であって、個人が自分のデータをどう扱うかまでは制限していません。つまり、個人が自分のデータを保持していれば、それを他国に持ち込んで治療を受けるといったことも可能なのです。インターネットの力を活用すれば、国境を超えた医療サービスの提供が現実のものになるのではないかと期待しています。
◯橋本 LLM(大規模言語モデル)は非常に強力なツールであり、今後深刻になるであろう人手不足の課題に対して、大きな可能性を持っていると感じています。医療の現場でこのようなツールをどう活用していくのか、それを考える上で、従来のツールとはまったく異なるルールや枠組みが必要になります。多くの関係者(ステークホルダー)がいる中で、そうしたルール形成に自分も関わっていけたらと考えています。
◯山本 マルチステークホルダーによる共創的なルールメイキングを進めていく上で、法律の側から関わる私たちは、ともすればブレーキをかける役割のように見られがちです。しかし、そうではなく、開発の初期段階から対話を重ねていくことで、共に適切なかたちでアクセルを踏むパートナーでありたいと思っています。
◯鈴木蘭美 本日のディスカッションを通じて、がんの早期発見・完治の実現を一日も早く目指したいという思いを強くしました。村井先生のご期待に応えられるよう、日本発で歴史に残る成果を出せるよう尽力したいと思います。

◯湯澤 医療DXの推進、AIの活用などにおいて、大学としても先進的な医療の研究開発に取り組む必要があると改めて感じています。今後は、医療DXを推進し、海外とのデータ連携もよりスムーズにできるようにしたいと考えています。また、日本の強みは、超高齢社会における豊富な健診データにあります。こうしたデータを活用し、将来的な健康予測にも役立てていければと考えています。
さらに災害医療の面では、南海トラフ地震のような大規模災害への備えとして、厚労省の電子カルテ共有サービスを通じて、最低限の医療データがどこでも確認できるような仕組みを整えることが重要です。
◯尾身 社会全体としては分断が進み、皆で同じ方向に向かうことが難しい時代になっているからこそ、ルール作りだけではなく「共感」を大事にし、本当の意味での対話が求められています。IT分野の専門家だけでなく、さまざまな分野の方々と、より深い対話の場を持ちたいと思います。
最後に、日本への期待についてですが、軍事ではなく、グローバルヘルスの分野でこそ、日本は世界のリーダーになれると信じています。多くの国々が日本に信頼を寄せており、今日のような議論を、もう少し平易な言葉に翻訳して世界に発信すれば、日本の文化だけでなく、経済にも大きな貢献ができると思います。
◯浅井(オンライン) 村井先生がおっしゃったように「標準化」が非常に重要だと感じています。さまざまなポリシーやルールに対応できるプロトコルやメカニズムといった、技術的な部分の標準化に、技術者として取り組んでいきたいと思います。
クロージング

「Closing Remarks」
David Farber, 慶應義塾大学大学院法務研究科特別招聘教授, サイバー文明研究センター共同センター長
今日は非常に興味深い一日でした—素晴らしいアイデアや思慮深いコメントがたくさんありました。ただ、少し注意点を加えたいと思います。
私たちはますます多くの個人情報をオンラインで利用できるように頼るようになっています。しかし、現実として、私たちのコンピューターは安全ではありません。現在の状態では、セキュリティを確保することはできません。そのため、この情報をオンラインに置くこと—中央集権的でも分散型でも—はリスクが伴います。もし私たちがコンピューターインフラのセキュリティ向上に本気で取り組まない限り、危険が残るでしょう。この問題は何年も続いており、ますます重要になっています。
もう一つ興味深い点は、今や私たち一人一人が驚くほど強力なコンピューターをポケットに持ち歩いていることです。今の安価なスマートフォンでも非常に高性能です。多くの人がスマートウォッチを身につけており、それもますます賢く、手ごろな価格になっています。これらのデバイスの多くは、基本的なAIモデル—例えば、大規模言語モデル(LLM)に基づいたもの—を実行でき、これにより世界中で医療へのアクセスを拡大する可能性が広がっています。
最後に一点、私はアメリカで医療情報の標準化に取り組んだことがあります。日本では少し簡単かもしれませんが、どこでも決して簡単ではありません。アメリカでは過去20年間にわたって試みてきました。メディケアが少しは助けになったかもしれませんが、大きな効果はありませんでした。そして、異なる国々を横断して見ると、ライセンス、責任、その他の規制の問題がさらに複雑にします。
したがって、可能性は非常に大きいものの、私たちが望む形でこれらの解決策を完全に実装するには、まだ多くの作業が必要です。
皆さん、ありがとうございました。

「閉会挨拶」
松本純夫, 独立行政法人国立病院機構東京医療センター名誉院長、厚生労働省顧問
本日は、あえて医療費の問題についてChatGPTに質問してきました。私は日本の医療費は本当に高いのか?という疑問をChatGPTに投げかけました。
2020年前半の統計をみると、OECD加盟国38か国の中で、対GDP比で医療費が最も高いのはアメリカで17%、次いでスイスが12.4%、ドイツが11.7%、フランスが11%となっており、平均は9%です。日本は10.9%で、これが本当に日本の財政にとって耐えられない状況なのか、というのが私の疑問です。
私が長年、経営に関わっていた東京医療センターでは、どれだけ医療者が頑張っても医業収支を黒字にするのが非常に難しいという診療報酬制度を実感しました。診療報酬制度はさらに厳しくなる状況にあり、現行の制度下では病院事業の黒字化は難しいと感じています。
ロボット支援手術—ダヴィンチを日本の保険診療体制に導入した2012年に私は厚労省の保険材料専門組織の委員長として関わりました。中医協から1台で1億から数億を超える購入金額で腹腔鏡手術と比較して非劣性しか証明できない手術機器を導入する必要があるか否かと批判され、費用対効果について深く悩んだことがあります。手術がしやくなる・外科医への負担が軽くなる利点を会議で述べました。しかし、ダヴィンチの販売価格とその手術の術後合併症の発生率が腹腔鏡手術よりわずかに低くなる点だけが取り上げられ、手術に関与する人間の負担を軽減すると言う機器が秘めている特性にまで議論が進まなかった残念な経験がありました。
しかし、その後、分子治療薬や抗体医薬など、より高額な医薬品が出てきたため、その費用対効果の問題はどこかに行ってしまったという記憶があります。その後、コスト評価についても議論が進み「医療技術評価」が行われることになりました。
このような診療報酬制度の下での財源不足に対応する制度変更や予算に関する議論について、ChatGPTは次のように答えてくれました。「民間の医療保険や患者自身が支払う医療負担、特に先進的な治療法が保険適用外の場合、患者が自己負担で支払うことが多い。これが影響を与える可能性がある。」私はこれが本当にその通りで良いのか、広く議論すべき問題ではないのかと感じています。簡単に言い換えれば、日本でも混合診療を進める、そしてその財源を国家予算からではない方策を講ずるべきと、AIが進めているのではないかと感じてしまいました。
これは、ChatGPTからではなく、私の私見ですが、これらの議論に抜けているのは、一生懸命働いている臨床医やメディカルスタッフの働きについてであり、医療従事者の負担軽減策は、お金に変えて評価されないということです。評価されているにしてもわずかです。この点について、AIでどうにかならないかと期待しております。
最後に、先ほど、橋田先生が熊本県荒尾市で行っている取り組みについて話されていましたが、このように国民に対して医療および医療技術のリテラシーを広げるために、AIやスマートフォンを活用する施策が進んでいることを期待しているとコメントさせていただき、私のクロージングリマークとさせていただきます。
(文:佐野仁美 写真:有馬俊)
→イベントレポート前半はこちら。
→さらに詳しいワーキングレポート「AIを前提とした医療の創生」はこちら。
参考資料
- 第一回セミナーレポート
【イベントレポート】2022.7.4開催 医療と健康のDXセミナー | 慶應義塾大学サイバー文明研究センター
- 第二回セミナーレポート
【イベントレポート①】2022.10.11開催 第2回医療と健康のDXセミナー「医療と健康に貢献するテクノロジー」
【イベントレポート②】2022.10.11開催 第2回医療と健康のDXセミナー「医療と健康に貢献するテクノロジー」
- 第三回セミナーレポート
 Contact us
Contact us